C.S.ルイス著作「悪魔の手紙」。
著者「C.S.ルイス」といえば,無神論から有神論へ回心した人物の一人ですね。
英国の児童文学者であり,優れたキリスト教の弁証家とうたわれています。
C.S.ルイス作品でも有名な「ナルニア国物語」は耳にしたことがあるかもしれません。
さて,それではC.S.ルイスがこだわりを持ち続けた定評本「悪魔の手紙」について、要約内容を見ていきたいと思います!
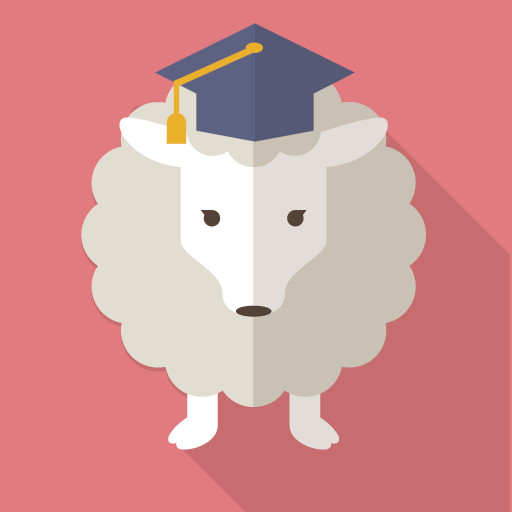
どこかユーモラスな設定でありながらも、超現実的な霊的誘惑について描かれています!
「悪魔の手紙」を読むコツ
「悪魔の手紙」の内容は,
「叔父の悪魔が甥の新米悪魔へ,人間を誘惑する方法を31通の手紙を通してアドバイスする」
という語り口調で進行しているため、悪魔視点で描かれています。
ここで読者に強いられるものは,悪魔の発言を逆手にとって読み解いていくことです。
本文:「およそ<敵>の狙いはこうだろう」
▼
意味:「およそ<神>の計画はこうだろう」
したがって,悪魔が発している言葉は「言い換えれば誘惑の対処法」とも捉えられるのです。
このことから、「悪魔の手紙」は「誘惑に打ち勝つための霊的書物」とも言えるのではないでしょうか。
また、神性が語られていることから神の御心と伺える発言として感じさせられる作品でもあります。
変換すべきキーワード|「悪魔の手紙」を読むコツ
先程の例にもあったように、作中に表記される<敵>は,三位一体における「父なる神」を指しています。また他にも「彼」は「キリスト」,「彼ら」は「精霊」を指します。
なお,「悪魔の手紙」にはこのような説明が一切なされていません。
そのため「『悪魔の手紙』を読むのは少し難しい」といわれる由縁があります。
・悪魔側の視点で書かれている
(叔父から甥っ子への手紙形式)
・次の言葉は意味を置き換えて読む
- 「敵」→「神」
- 「彼」→「キリスト」
- 「彼ら」→「精霊」
- 「やつら」→「人間たち」
- 「われわれ」→「悪霊」
- 「われらの父」→「サタン」
悪魔について誤った認識
「悪魔の手紙」のまえがきでは,「悪魔は嘘つき」であることが主張されています。
ここで,人間が悪魔について考えたときに陥りやすい誤りが2つあります。
- 悪魔を全く信じない態度
- 悪魔に過度の不健全な関心を寄せる態度
「悪魔を全く信じない唯物論者」と「過度に不健全な関心をもつ人」,こういった傾向にある人を悪魔は歓迎していると注意書きがあります。
例えば,マンガや小説などの影響によって、悪魔を「可愛い」などと思ってはならない事です。
悪魔はグロテスクな存在であることが主張されています。
参照:「悪魔の手紙」
悪魔の手紙【 内容紹介 】
『悪魔の手紙』の内容は,叔父の悪魔スクルーテイプが甥っ子の悪魔ワームウッドへの手紙内容をそのまま表記したものです。
設定として甥っ子は「新米悪魔」であること。また,一人の人間に悪魔が誘惑を担当していることです。(基本的に1:1の関係)
本編では,あらゆる誘惑が日常に溶け込まれており,とてもリアルに描かれています。

さて,『悪魔の手紙』は第1信〜第31信(全31通の手紙)あります。ページ数は全136Pほどです。
実際に読むと雰囲気がわかりますので,参考として「第1信〜第3信」の内容を一部ピックアップしました。
ピックアップ箇所は、人間に対する誘惑の働き方や、人間と神の性質や考え方についてです。
次の見出しにて「悪魔の手紙」「第1信」〜「第3信」までの内容をピックアップしてご紹介しています。
CSルイス「悪魔の手紙」の内容は、「少し難しいですが読めなくはない」といったレベルです。
ファンタジーに収まる本と言い切るにはあまりに現実味が高く、読み進んでいくほど、「これは誘惑だったのか。こんな経験は自分にもあったかも」と感化されるほどです。
それでは「悪魔の手紙」の内容の一部を見ていきたいと思います!
『第1信』
CSルイス「悪魔の手紙」第1信
(一部文節を省略した引用です)
教会に近づけさせない誘惑
ワームウッド君に。
きみはきみの担当の男にたいして読書指導をこころみ,その一方,例の唯物論者の友人としばしば会うように働きかけているらしいね。
だが,それは少しばかり素朴すぎではないだろうか。
やつを論証に明け暮れさせておけば,〈敵〉の魔手から守りおおすことができる——きみはそう考えているようだが。
やつがもう二,三世紀前の人間であれば,そういうことも可能だったかもしれない。
そのころの人間はまだ,あることが証明されているときと,いないときとをはっきり区別しており,証明されていれば本気で信じた。
彼らはまた思考を行動と結びつけていて,一続きの推論の結果にもとづいて,自分の生き方そのものを変える気が大ありだった。
ところが週刊誌や,それに類する他の武器の力を借りて,われわれはそうした態度をおおかた変えてしまった。
きみの担当の男は幼いころから,互いに矛盾するいくつもの哲学が自分の頭のうちに一緒くたに跳ねまわっているのに慣れっこになっている。
いかなる教説についても,まず「真理」であるか,「虚偽」であるかといった観点に立たず,「アカデミック」か,「実際的」か,「古くさい」か,「慣習的」か,「非情」かを問う。
したがって,論証ではなく,難しい術語の羅列こそ,この場合,きみの最良の味方なのだ。
論証をさせずに,そうした術語を漠然と与えておけば,やつは教会に近づかないだろう。
唯物論を信じさせようとしても時間の無駄だ。
むしろ,唯物論は強烈だ,もしくはしたたかだ,勇気ある哲学,未来の哲学と思わせるのだ。
やつが心にかけているのはそうしたことなのだから。
論証で厄介なのは,自分の議論の正しさを証明しようとしているうちに,戦場が知らず知らずに,<敵>の陣地内に移ってしまうことだ。
<敵>にも論証はできるからだ。
もっとも,実際的なプロパガンダの類いは,われらの側が長けているがね。
(※プロパガンダとは・・・宣伝のこと。特に、特定の主義・思想についての(政治的な)宣伝を指す)
それは数世紀の歴史が明らかにしている通りだ。
きみの任務は,感覚的経験の流れそのものにやつの注意を引きつけることだ。
それこそが生きているということ,「実生活」—リアル・ライフだと考えさせたまえ。
「リアル」とはどういうことか,その点について自問させてはならない。
インスピレーションへの誘惑
かつて私は健全な無神論者の誘惑を任されたことがある。
その者はいつものように大英博物館の図書室で本を読んでいるうちに,彼の思考作用がわたしからみて好ましくない方向にそれだした。
そのときには<敵>はもちろん,すでに彼のかたわらにきていた。
みるみるうちに,私が二十年かけて積み重ねてきた成果が揺らぎ出した。
しかし,私は慌てなかった。
慌てふためいて論証という手で自分の立場を防衛しようとしていたら,わたしはおそらく敗北していただろう。
だが,わたしはそんな愚か者ではない。
わたしはただちに彼のうちでわたしの支配の手がもっとも確実におよんでいる部分に働きかけて,そろそろ昼食を取る時刻ではないかと提案した。
<敵>もさるもの,いま頭に浮かんでいる問題は食事より重大だという反対事案をただちにしたらしかった。
(らしかったと書いたわけは,彼への<敵>の語りかけを小耳にはさむことすら,われわれにはできないからだ。)
少なくともわたしはこれが,<敵>の戦法ではないかと察している。
というのは,わたしが「そうだとも。昼食前にそそくさと取りくむには,この問題は重大すぎる」と<敵>の戦法そのものを逆手に取って,暗示してやると,やつは大いに元気づき,わたしがさらに「昼食をすませてから,新鮮な気持ちで取り組んだらいいさ」と付け加えたときは,すでに戸口にむかって歩き出していたのだからね。
いったん通りに出ると,もうこっちのものだった。
私は彼に,大声を上げて新聞を売っている売り子や,七十三番バスが通過するさまを見せてやった。
そんな当たり前の光景を見せることで,彼が大英博物館の階段を下りきる前にわたしは彼をてもなく自分の支配下に取り戻していた。
すなわちわたしは彼に,本だけを相手にひとりで閉じこもっていると,とかくおかしな考えが頭の中に入りこむが,「実生活」という一服の清涼剤(具体的にはバスとか,新聞の売り子のことだが)の効きめはあらたかで,おかげで,さっきちらっと頭に浮かんだ「ああした考え」が本当であるわけはないと,はっきり悟ることができた——と思い込ませることに成功していた。
この男はいまではわれらの側の家に安住している。
思い込ませる誘惑
どうだ,少しはわかりかけてきたかね?
何世紀も前にわれわれが人間のうちに作動させたプロセスのおかげで,人間は見慣れているものが目の前にあるあいだは,見慣れていないものをほとんど信じられなくなっている。
彼らがいつも物事の当たり前さを実感するように働きかけたまえ。
とりわけ実在する諸科学を,キリスト教にたいする防衛手段として用いようと試みてはならない。
そうした諸科学は人間に積極的な影響を与えて,触ることも,見ることもできない実在について考えることを奨励する。
現代の物理学者のうちにも<敵>に寝返った悲しむべき実例がいくつかあった。
きみの担当の男が科学をかじりたがるならば,経済学とか,社会学に関心を集中させて,やつらの信奉する「実生活」から離れないようにさせるのだ。
だが何よりいいのは科学書を真剣に読ませる代わりに,自分は*消息通だと思いあがらせ,たまさか聞きかじったり,読んだりしたものを,まるで「現代の科学的研究の成果」であるかのように思い込ませることだ。
(※消息通・・・ある方面の事情をよく知っていること)
忘れたりしないでくれたまえ。
きみに与えられている役目は,やつを混乱させることなのだよ。
きみら若い悪魔連中がしゃべるのを聞いていると,悪魔の本務は教えることなんじゃないかという気がしてくるのだがね。
参照引用:CSルイス著作集「悪魔の手紙」第1信より
どうやら新米の悪魔は担当している人物を唯物論に傾けるために書物を読ませたり,唯物論者と友達になるように誘惑を働いた様子です。
『第2信』
CSルイス「悪魔の手紙」の第2信の内容です。
第2信から「彼」という言葉が出てきます。
冒頭であるように「彼」は「キリスト」のことを指しています。
新米の悪魔が担当する人物はクリスチャンになりました。悪魔は絶望的な気分でありながらも希望を見出します。成人してからクリスチャンになり,神の陣営にしばらく滞在したのちに,悪魔の側に取りもどされた者が何百人もいることを甥の悪魔に伝えます。
教会へ通い始めた人への誘惑
けしからんことに,やつはクリスチャンになってしまったんだね——。
さて,当面われわれとしては,現在の状況をせいぜいうまく利用する必要がある。
絶望するにはあたらない。
成人してからクリスチャンになった人間で,<敵>の陣営にほんのしばらく滞在したのちに,われわれの側に取りもどされた者が何百人となくいるのだから。
やつの習癖は,精神的なものにしろ,生理的なものにしろ,いまだにことごとく,われわれに有利にはたらいているのだからね。
目下のところ,われわれにとってもっともありがたい味方は<教会>そのものだ。
誤解しないでほしい。
私が意味しているのは,時間と空間の全域に広がりをもち,永遠そのものにがっちりと根ざしている霊の<教会>,あまたの軍旗をかかげた無敵の軍勢のように恐ろしい,かの<教会>ではない。
それはわが方の,もっとも大胆な誘惑者をさえ,不安におののかせる偉容を備えている。
しかし幸いなことに,真の<教会>はやつら人間どもにはまったく見えないのだ。
きみの担当の男の目に見えるものにしても,ゴシック建築まがいの建物だ。
中に入って行くと,如才なげな微笑を浮かべて,あたふたと近づいて本を二冊渡してくれる。
一冊は小冊子で,その中には,とてもじゃないが二人のどっちにも意味がよくわかりそうにない祈祷文が納められている。
もう一冊は宗教的な叙情詩を無秩序にあつめたものだが,たいていは詩としてはいただけぬ代物で,おまけに活字がばかに小さい。
席について,あたりを見まわすと,隣人たちのうち,これまでできるだけ接触を避けてきたような連中の顔がちらほら見える。
きみはそうしたたぐいのやつの隣人たちを,大いに当てにしたくなるだろう。
君の担当の男が,「キリストの身体なる教会」といった表現と,現に隣にすわっている連中の顔とを引きくらべるようにそそのかすことだ。
もちろん,隣席に実際にどんな人間どもが座っているか,その内面がどうかは問題ではない。
きみはそのうちの一人が,じつは<敵>の側の勇敢な戦士だということを知っているかもしれない。
だが,そんなことはどうでもいい。やつはありがたいことに愚かだ。
周りの者が賛美歌を調子はずれに歌ったり,キューキュー鳴る靴をはいていたり,みにくい二重あごだったり,妙な服装をしていたりすれば,そういう人間が信ずる宗教も,いささかこっけいなものに違いないと頭から決めてかかるだろう。
「理想」への誘惑
この段階でやつの頭の中にあるクリスチャンの理想像は,彼本人は精神的なイメージだと思い込んでいるが,じつは絵画的な性質が強い。
たとえば,やつの頭の中にあるクリスチャンの像は,古代ローマ時代の人間の,トーガをまとったり,甲冑を身につけていたり,素足にサンダルをはいていたりといった姿だろう。
教会にきている,他の連中が現代風の服装をしているということにしてからが——もちろん無意識のうちにではあるが——実際のところ,やつには受けいれがたいのだ。
ただし,そうした考えを表面化させないこと,教会にくる人間の外見がどのようであるべきだとやつが考えているのか,けっして自問させないことだ。
今の時点では,すべてを漠然とさせておくにかぎる。
そうすればやつのうちに,地獄が提供するたぐいの,あの独特の明晰さを生じさせることに成功するだろうし,きみはその成果を未来永劫まで楽しめるわけだ。
失望へ付けこむ誘惑
だから,教会員となったのちの最初の二、三週間のあいだにかならずやつの心のうちに訪れる失望や落ち込みに,せいぜい働きかけたまえ。
<敵>はすべての人間の努力の発端において,そうした失望が起こることを許している。
その種の失望は,恋人同士だった二人が結婚し,ともに生きる道を学ぶという人生の真の課題に取り組みはじめたときにも起こる。
つまりそうした失望は人生のすべての分野において,夢多き憧れが苦しい実践へと推移する際に,必然的に人間のうちに生まれるものなのだ。
人間を一変させるために<敵>は,この二本足の獣と不自然きわまるつながりをもち,それによって全霊界を堕落させようという執念をいっかな捨てようとしない。
人間が自由であることを望むあまり,<敵>は人間の前に彼が置いた,いかなるゴールにもせよ,単なる愛情とか,習性だけをよしとして,彼の手で運んでやろうとはしない。
人間が「自力で」ゴールにたどりつくように,彼自身は手を出さない。
そしてまた,そこにわれわれのチャンスがあるのだ。
しかし覚えておきたまえ。それは同時にわれわれにとって危険でもある。
いったん人間が求道の最初に彼を襲う失望という,この不毛の試練を通過するなら,感情に依存することがより少なくなるだろうし,したがって容易には誘惑されなくなるだろう。
ここまで書いてきたことは一応,礼拝中にまわりの席にいる連中がやつの失望に合理的な根拠を与えない場合だ。
きみがなすべきことは簡単だ。
やつの胸のうちから,「こんなわたしでも何らかの意味で自分をクリスチャンだと考えることができるとすれば,まわりの人たちがそれぞれに難点をもっているからといって,その信仰を偽善だとか,慣習的だなどと決めつけることはできないのではないか」といった疑問を遠ざけるだけでいい。
たかが人間の心とはいえ,そんなわかりきった考えが浮かばないようにすることがはたしてできるものだろうか,ときみは反問するかもしれない。
ところがこいつはきわめて容易なのだよ。ワームウッド。
やつをうまく操れば,やつはとてもじゃないがそんなことに思いいたらない。
やつの場合,<敵>との馴染みはごく浅いから,真の謙虚さなどというものはまだ身についていない。
やつの自分の罪深さについての告白は,祈りのうちにおいてであれ,単なる口真似にすぎない。
心の奥底ではやつは,回心してやったのだから,<敵>に相応の貸しをつくったくらいに考えており,ああした「ひとりよがり」な,平凡な連中に肩をならべて,あえて身を屈して教会に行くというのは,なかなか謙虚な行動で,自分としては大きな譲歩をしているわけだなどと考えているのだからね。
そうした心境にできるだけ長くとどめておくことだ。
参照引用:CSルイス著作集「悪魔の手紙」第2信より
『第3信』
CSルイス「悪魔の手紙」第3信の内容です。
『第3信』では,新米悪魔が担当する人物の母親の誘惑を担当している別の悪魔グラボーズが登場しています。新米悪魔が担当する男とその母親はどうやら関係が良好ではない様子。叔父の悪魔はその点に仕掛けるように働きかけます。
自己の内面に関心を向けさせる誘惑
きみの担当の男の,母親との関係について聞かせてもらって大いに喜んでいる。
だがこの際きみなりの利点を最大限に活用すべきじゃないかね。
〈敵〉のやりロを思い出したまえ。
〈敵〉は中枢部をまず占拠して,そこから働きかけるのを得意としている。
すなわちまずやつの意志を抑えて,そのうえでやつの行為をしだいしだいに新しい旗印のもとに取りこもうとするだろうから,母親にたいするやつの行為にいつなんどき〈敵〉の感化がおよぶか,わかったものではないのだ。
きみとしては先手をうっておくにこしたことはないだろう。
母親を受けもっているグラボーズと緊密に連絡を取りあって二人で共同戦線を張り,やつらの家庭のうちに憤懣とか,こすからい嫌がらせを日常化させたまえ。
それには,次のような方法が有効だろう。
やつの関心をもっぱら内側,すなわち心の内奥にむけさせること。
やつはこのたびの回心について,もっぱら自分の内面に起こったことだと考えており,したがってその関心は現在のところ,主として彼自身の心の状態というか,さしさわりのあるものを残らず取り去った,いわば浄化版とでもいうべきもの(きみは,その浄化版だけをやつに見せてやるべきだろう)にむけられている。
こうした傾向を大いに奨励したまえ。
やつの心をきわだって高級な精神的義務にむけるようにさせ,その一方,およそ基本的な義務からそらすわけだ。
人間には,自明と見えることをばかにして問題にもしないという傾向がある。
そうした特質はわれわれにとって大いに好都合なのだが,これをいっそう助長するといい。
たとえばやつが一時間たっぷり自己吟味をしても,やつと一つ屋根の下に住んでいる者,あるいはやつと同じ職場で働いたことがある者にはきわめて明白な,やつに関する事実に,やつ自身はてんで思いいたらないというような,そんな状況に立ちいたらせるべきだろう。
むろん,きみとしてもやつが母親のために祈るのを阻止するわけにはいかない。
しかしその祈りをわれわれなりに無害にする手段はあるのだよ。
すなわち,その祈りをきわめて「精神的な」ものとして,やつにいつも母親の魂の状態を気にかけるようにさせ,その一方,彼女のリウマチの痛みといった実際的な問題にはまるで無関心なように仕向けることだ。
祈りの対象を想像の人物へ向ける誘惑
ここからわれわれにとって好都合な結果が二つ生ずる。
まず,こうした状況下ではやつの関心は一貫して,やつが母親における罪と考えている行為に集中するだろう。
そこでちょっと水をむけてやればやつは母親の行動のうち,やつ自身にとって都合がわるいもの,あるいは癇にさわるものを何によらず,彼女の罪と考えるようになる。
こうしてきみは,やつがひざまずいて祈っているときにさえ,その日,やつが母親から受けた傷をちょっとばかり余計にうずかせてやることができる。
なに,大してむずかしいことではない。
それどころか,きわめて愉快だろうよ。
第二に,母親の魂についてやつがいだいている見解はこまやかな理解に裏づけられているとはいいがたく,むしろしばしば誤っているから,やつが彼女のために祈るとしても,ある程度まで,現実には存在しない想像上の人物のために祈っていることになる。
そこがきみの付け目なのさ。
その想像上の人物が日ごとに母親その人——朝食の食卓で耳の痛いことを言う——と,はなはだしく懸けへだたるようにさせたまえ。
きみの努力が実を結ぶと,母親その人と想像上の母親との隔たりはおそろしく大きくなって,息子であるやつの祈りから何らかの考えが生まれたり,感情があふれたりして現実の母親にたいするやつの態度が変わるといったことは,一切なくなるだろう。
わたし自身の経験でも,担当の男をうまく操るうちに本人が妻なり,息子なりの「魂」のための熱烈な祈りから一転して,実在する妻や息子をしたたかにぶん殴ったり,侮辱したりしても少しも良心に痛みを覚えなくなる例がしばしばあった。
同居関係における誘惑
二人の人間が長年にわたって一緒に暮らすうちに,往々にしてそのうちの一人の声音や表情が耐えがたいほど,もう一人の癇にさわるということがあるものだ。
きみとしては,そうした点を取っかかりにするといい。
きみの担当の男に,母親が眉毛を吊りあげたときの表情(やつは幼少のころから,この顔つきをうとましく思っていたのだが)を嫌というほど意識させ,あれが自分にはたまらないのだと思わせたまえ。
先方は,こっちがそれを嫌がっているのを百も承知していながら,怒らせるためにわざとそうした表情を自分にむけるのだと考えさせるがいい。
きみがうまく立ちまわれば,やつはすべては自分の勘ぐりにすぎないということに気づかないだろう。
もちろん,自分の口調や顔つきにしたところで,母親にとって同じように腹だたしいのかもしれないなどと気をまわさせないように気をつけたまえ。
彼には自分の顔が見えず,声にしてもとくに意識しているわけではないから,まあ,これは容易だろう。
社会生活が進化すると,家族間の憎しみは,文字づらではまったく無害と響くが(つまり言葉のうえでは攻撃的と言えないのに),ある声音で,もしくはある特別な瞬間に言われることで,顔を平手でピシャリとぶたれたのとほとんど同じ効果を与えることができるようになる。
このゲームを持続させようと思うなら,きみとグラボーズは,めいめいの担当の愚か者が物事を判断するのに一種の二重基準を用いるように,取り計らったらいい。
つまりやつは自分の言葉が母親に受け取られることを要求する一方,母親の言葉の方はその声音と文脈を,自分の思いすごしかもしれない,嫌みな意図までひっくるめて,神経をピリピリさせて受け取るようになるわけだ。
母親の方もやつにたいして似たような態度を取るように。
そこはまあ,グラボーズの腕のふるいどころだろう。
そうこうするうちに両者はロげんかのあげく,自分にはまったく悪いところはないと,まあ,ほとんど信じこむに違いない。
きみがよく知っているように,息子は「わたしは母に,夕食は何時になるのかときいただけなのに,何だって,あんなふうにいきりたつんだろう?」と憤遜の思いをいだくわけだ。
こうした習慣が確立すると,当事者は相手を怒らせるためにある発言をしながら,その相手がいきりたつと根にもつといった,愉快きわまる状況が生じることになる。
さて最後にきみに頼んでおきたい。
やつの母親の宗教上の立場について,ぜひとも聞かせてもらいたい。
彼女は息子の生活のうちに生じた,新しい因子について,いささかでもねたましく思ってはいないかね?
息子には幼いうちからチャンスをさんざん与えてやったにもかかわらず,息子がこの自分からでなく,他人から何かを,しかも成人したのちに学んだなんてと憤慨してはいないだろうか?
何をありがたがって,あんなに大騒ぎをしているのかと心外に思ったり,大して苦労もせずにと気をわるくしてはいないか?
例の<敵>の書物に出てくる,放蕩息子の兄の場合をよく心に留めておくがいい。
参照引用:CSルイス著作集「悪魔の手紙」第3信より
おわりに
CSルイス「悪魔の手紙」いかがでしたか?
日常に溶け込む誘惑が現実味を帯びていますね。
筆者はこの本を勧められたとき,霊的な書物として,あくせくしながらも読み勧める魅力に引きつけられた経験があります。
そのかいもあって,誘惑に対しては本書の視点を参考に役立てています。
今回は,CSルイス「ナルニア国物語」に続き,映画化されるとの情報もあった「悪魔の手紙」でした。
最後に少し,冒頭部分で紹介されている「ルター」と「トマス・モア(聖人)」の言葉を挙げておきます。
ルター「悪魔のいちばんよい撃退法は,もしも彼が聖書の言葉を聞かされても降参しないなら,嗤ってやること,軽蔑することだ。悪魔は,ばかにされると平気ではいられない」
トマス・モア「悪魔は誇り高い霊で・・・嘲笑を聞き逃すことができない」
引用:CSルイス著作集「悪魔の手紙」







