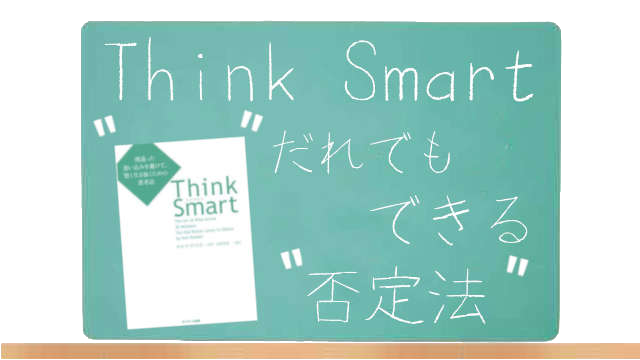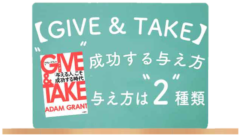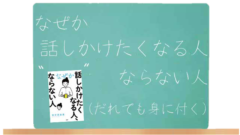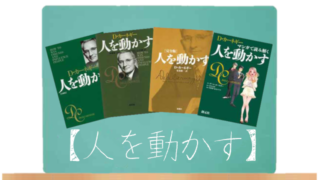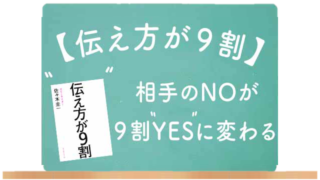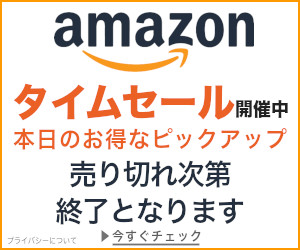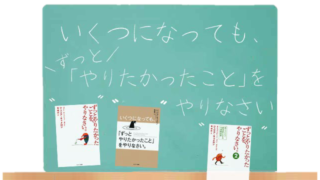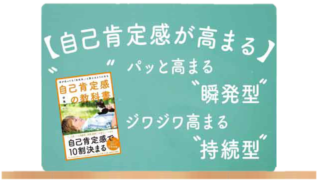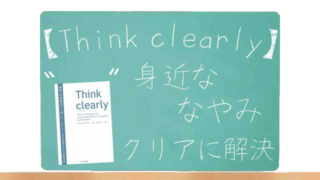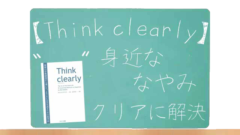2020年1月に出版された書籍「Think Smart」(著:Rolf Dobelli/ロルフ・ドベリ)。
前作「Think clearly」の続編となります。
「Think Smart」の内容は、「何が成功をもたらすか」ではなく「何が成功を妨げているのか」に注目して解説されています。
その理由として説明されているのは、成功の要因をハッキリ答える事は難しいため不明確ですが、成功の妨げとなる要因を答える事は明確だからです。
また「Think Smart」は全52原則が「間違った思い込みを避けて賢く生きる」という名目で紹介されていますが、この原則の特徴は誰でも出来る方法だという事です。
この「誰でも出来る方法」と言える理由は「否定法」にあり、これを活用して著者は解説されています。

今回は「否定法」も含めて「Think Smart」の要約ポイントをまとめました!
Think Smart の原則を誰でも行える理由は「否定法」にある

「Think Smart」にある全52原則は「間違った思い込みを避けて賢く生きる」という名目で紹介されていますが、この原則の特徴は誰にでも行えるる方法だという事です。
そう言われる根拠は否定法にあります。
否定法とは、何かを証明するために、その何かの要素以外を否定していく方法です。
これは例えば、「人間とは何か」の問いに答えることは難しいですが、人間ではない要素(肌の色が緑ではない、羽毛がない等)を挙げていくと、「人間とは何か」の答えに近づいていくといった感じです。
例えば、実際に「否定法」を使った作品や名言は次のようになります。
- 「ミケランジェロ」(彫刻家)
ダビデ像を制作するときに否定法を用いて、「ダビデらしくないもの」を取り除くことで完成させる - 「アリストテレス」(哲学者)
否定法を用いた発言→「何が幸福かを答えることは難しいが、何が幸福でないかを言うことは容易だ」
「Think smart」はこの否定法を活用して、「成功に必要な原則」を教えるわけではなく、「成功の妨げを避ける原則」として解説しているのです。
同時にそれは、誰でも出来る方法と言われている理由としても挙げられています。

「成功に必要なもの」ではないので、才能やセンスを必要としないということです!
【Think Smart】間違った思い込みを避けて賢く生きるための原則

「Think smart」では、「何が人生の成功を妨げているのか」の正体が分かるように、「間違った思い込みを避けて賢く生きるための原則」が紹介されています。

今回は「Think smart」の全ての原則の中から7つピックアップしました!
協力を得たいときの原則
それでは「Think Smart」の原則①人から協力を得たいときに活用できる原則を見ていきます。
ここでは、人から協力を得たいときに間違いやすい認識として、「お金で人から協力を得られる」と思い込んでしまう問題について挙げられています。
これに対して「Think Smart」の主張は、人はお金で行動するのではなく、人は理由によって行動すると解説しています。
- 「理由」があるだけで意外と人は動く
- 「理由」はないよりあったほうがいい
- お金で協力を仰ぐと反感を買うことがある
ここで、理由によって人を動かす例を一つ挙げます。
次のような通行止めの会話は、運転手なら誰もが経験しているかと思います。
- (協力を仰ぐ)
Aさん「ここは通行止めです」 - (不満)
Bさん「なぜですか?」 - (理由)
Aさん「工事中です」 - (行動)
Bさん「工事中でしたか。分かりました。迂回します」

これは「理由」を述べて相手の行動を促している基本的な例です!
ここで例えば、理由を伝えて協力を求めるのではなく、お金で協力を求めようとした場合、相手から反感を買ってしまう可能性が考えられます。
次の例は、「お金」もしくは「理由」によって説明されたとき、どちらの人に対して行動したくなるかというものです。
(問題)次の主張を見て、AさんとBさんのどちらを応援したくなるでしょうか?
Aさん「私は3年間勉強しました。よろしければ私の試験を応援してください」
Bさん「あなたにお金を差し上げます。よろしければ私の試験を応援してください」

心から応援したくなるのは、理由を述べたAさんではないでしょうか。
「理由」をつけるときのポイント
「理由」をつけて人の行動を促すときは、物語を伝えることが効果的です。
例えば、貧困地への寄付金を募集する場合、現地の状況を数値や統計データで理由を付けるよりも、現地の人を写真で見せたほうが募金額が集まったという検証結果があります。
つまり、理由をつけて人を動かすときは統計のデータやお金ではなく、物語が共感を得やすいのです。

人を動かすときはお金や数字よりも物語が効果的!
このように、「Think Smart」は成功の妨げを避ける方法を教えてくれるのです!
何かを選択するときの原則
「Think Smart」の名目「間違った思い込みを避けて賢く生きる」にある、何かを選択するときに活用できる原則について紹介します。
ここでは、人が選択するときの特徴について述べられています。
- 「決断」は人を疲れさせる
- 「標準案」に従う
「決断」は人を疲れさせる
人は決断しようとすると体力を消費してしまいます。よって「決断疲れ」をおさえることがポイントになります。
この決断疲れの性質を上手くビジネスに用いた店舗が「IKEA」です。
「IKEA」の建築構造は、デパートの真ん中にレストランを配置することで、買い物による「決断疲れ」をケアして、再び来店させる狙いを備えているのです。

人は体力があるときに大きな決断をするので、疲れさせないように配慮して利益を上げているのです!
「標準案」に従う
「標準案」とは、一般的な案(又はお手頃なもの、コスパが良いもの等)のことを指しています。
例えば、商品売り場でビールを購入しようと考えている消費者にワインを売りたいとき、販売者はお手頃価格のワインを推しに出そうとします。
この場合だと、ワインの中でもお手頃価格でちょうど良いハウスワイン(標準案)が売り場に出されることになります。
そうすることで、様々なニーズを持つ人にワインを購入しやすくしているのです。

スーパーや薬局などで「商品が安くて買いやすい!」と感じるのは、販売者が「標準案」に従っているからなのです!
標準案によって、多くの人が標準なものを選ぶ行動を取るようになります。
そのように行動を取る理由には、人には「デフォルト効果」が働くからです。
デフォルト効果
デフォルト効果とは、「人は標準なものを選ぶ傾向にある」という心理学用語です。
例えば、商品説明で「こちらの商品は赤色がメインで、他には青と黒がございます」と勧められた場合、標準色と説明された赤色がもっとも売れるといった検証結果があります。
また、臓器提供における検証もあります。
「サインすることで臓器提供の意志を表す記入用紙」
「サインしないことで臓器提供の意志を表す記入用紙」
2つの記入用紙で比較した結果、臓器提供した人が前者は40%となり、後者だと80%へと増加を見せました。
参照:「Think Smart」
注目すべきポイントは、後者においてサインしないことがデフォルトとなっていることです。
このことからも、人はデフォルトとして設定されている方を選ぶ傾向があると判明されたのです。

スマホの設定を標準のままにしている人も多いですよね。このこともデフォルト効果が働いていると考えられるのです。
嫉妬をしてしまうときの原則
「Think Smart」の名目「間違った思い込みを避けて賢く生きる」において、嫉妬をしてしまうときの原則を紹介します。
嫉妬の性質を知ることで、成功を妨げる間違った思い込みを避けることができるのです。
ここでは、アリストテレスの言葉が参考になります。
「陶芸家は陶芸家を妬む」
この言葉は、自分と業種が同じ人だと嫉妬が生まれることを意味しています。
逆に嫉妬しない相手とは、自分と全く関係ないジャンルの人です。
つまり、嫉妬をしないコツは「自分の得意分野で上を目指す」ことになります。どんな分野でも「No1」になると妬まないようになるのです。
こちらの内容は、前記事 Think clearly「能力の輪」でも主張されていました。
ポイントは「自分にできる事だけに集中すること」と解説されています。

「自分にできる事だけに集中すること」は、自己肯定感が高まる効果もあります!
自己肯定感については 別記事「自己肯定感の教科書」を参考にして見て下さい!
仲間を作るときの原則
「Think Smart」の名目「間違った思い込みを避けて賢く生きる」において、仲間作りをするときの原則を紹介します。
仲間を作るポイントは「共通点」です。
共通点が仲間を作る理由として、「内集団バイアス」が挙げられます。
内集団バイアス
「内集団バイアス」とは、共通点がある人同士の集団が友好を深めようとする働きを指します。
実際に検証された実験があります。
全く関係ない人同士が集められ、「その集団に共通性を持たせるためのフィクション」を宣言しました。
宣言されたフィクションの内容は、「あなたたちは芸術への関心が高い人たちだ」です。
すると、宣言された集団は「私たちはそういう人なんだ」と共通点を認識して、集団内で友好を深めようとしたのです。
集団はメンバー同士に共通点があると、仲間だと認識する傾向が働き、親睦を深めようとすることが判明しました。

自分が作った料理を美味しく感じるのは、「内集団バイアス」がかかっているからだそうですよ!
友好の育みに活用できる「内集団バイアス」ですが、その一方で「外集団バイアス」が生じてしまう傾向をもちます。
「内集団バイアス」は「外集団バイアス」を生む傾向がある
「内集団バイアス」は特徴として「NIH症候群」を持ちます。
「NIH症候群」とは、自分たちで作ったものを良いものと感じ、それ以外は良いものと感じないこと。(Not Invented Here syndrome)
「NIH症候群」は、自分ではないものを無機質のように感じてしまう人間の傾向として表れたものです。
よって、「内集団バイアス」は上手く活用すると友好を深めることが出来ますが、それと同時に、部外者に対して攻撃性を持った集団を生む傾向があるのです。

仲間作りをするときは「外集団バイアス」に気をつける必要があると「Think Smart」は主張しています!
宣伝するときの原則
「Think Smart」の名目「間違った思い込みを避けて賢く生きる」において、宣伝をするときの原則を紹介します。
プロパガンダ(広告活動)の性質について「Think Smart」は主張しています。
特定の思想を植え付けるための広告活動のこと。
プロパガンダに秘められた性質
プロパガンダとして映画や広告物を見せると、その作品への評価は低くなる傾向があります。
なぜなら、プロパガンダだと自覚しながら当人が見ているからです。
ところが、プロパガンダの効果は2ヶ月後に表れます。
更に、人は自分が見た映像や記憶の情報源を2ヶ月後に忘れるといった検証結果があります。
このことから、プロパガンダによって見せられた情報源を忘れて、情報の内容だけが残るようになると言えるのです。
プロパガンダは後から効果が出る
プロパガンダを見せても警戒するためすぐに効果は表れにくいですが、人は2ヶ月後に情報源を忘れやすく、情報の内容だけが人の記憶に残ります。
プロパガンダは、関心や興味を全くもっていない人にも効果があるのです。

将来性を見据えて広告効果を打ち出すテクニックとして、プロパガンダは活用できるという内容でした!
参照:Think Smart
計画するときの原則
「Think Smart」の名目「間違った思い込みを避けて賢く生きる」において、計画するときの原則を紹介します。
計画の達成において忍耐や節制は欠かせませんが、これらは体力を消耗してしまいます。
そこで、忍耐や節制をするときには押さえておくべきポイントがあるのです。
- パート分けして期限を決める
- 余計な情報を排除する
- 計画を達成した後の自分にご褒美を用意する
また、計画を達成できなかった理由に多く挙げられるのが、予想外の出来事が起こることです。
この予想外の出来事への対策としては「死亡前死亡分析」が挙げられます
計画達成のために「死亡前死因分析」を活用する
「死亡前死因分析」とは、終焉が起こることを事前に予期し、その原因を探ることで成長戦略を促すマネジメント手法です。
例えば、1年後に計画が大失敗することを考えて、最悪な事態の回避策を用意するといった感じです。

「死亡前死因分析」は重要な手法として挙げられています!
「最悪な事態への回避策があって、初めてその計画が上手くいく」と言われるほどです!
期待するときの原則
「Think Smart」の名目「間違った思い込みを避けて賢く生きる」において、期待するときの原則を紹介します。
「して良い期待」と「してはいけない期待」がある
「Think Smart」によると、何かに期待するときには「して良い期待」と「してはいけない期待」があります。
- 「して良い期待」
→ 自分や相手に期待すること - 「してはいけない期待」
→ 自分の影響下にないものに期待すること
自分や相手には期待しても良いが、自分の影響下にないものには期待してはいけないと「Think Smart」は主張しています。
期待によって才能を開花させた検証
「教師期待効果」と「プラセボ効果」というものがあります。
- 「教師期待効果」
→ 教師が期待することによって学習者の成績が向上する効果が表れること - 「プラセボ効果」
→ 効き目のない薬でも、飲むときに「効き目がある」と思い込むと症状が改善する効果が表れること
次に、「教師期待効果」と「プラセボ効果」を組み合わせて才能を開花させた検証内容です。
学習者の全体から20%の人だけに、「あなたたちは、これから才能が開花する潜在性を秘めている」といった言葉をかけます。
すると、声をかけられた20%の人が周囲の人と比較して、著しく才能を開花していく結果となりました。

自分に対する期待や自信、自己肯定感を高めると、自分の能力が開花していくのです!
【Think Smart】要約まとめ
今回は全52の原則から、重要な原則を7つピックアップして要約しました!

今回は「Think Smart」の要約まとめでした!
最後までお読み頂きありがとうございました!
前記事「Think clearly」はこちら