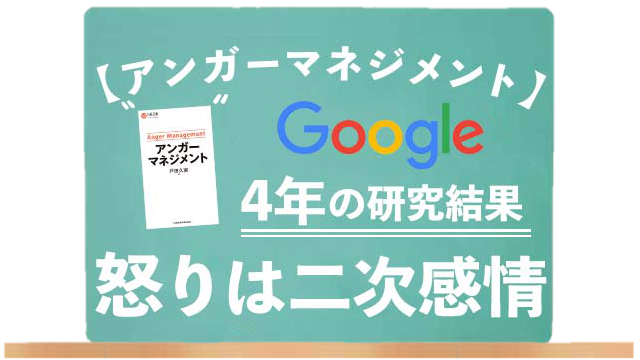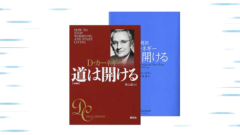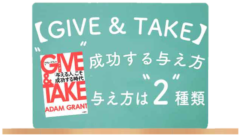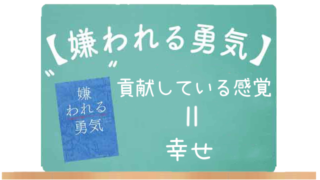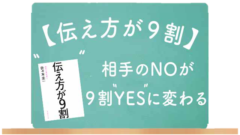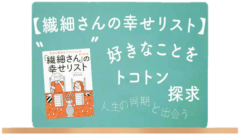2020年3月に出版された戸田久実さん著作「アンガーマネジメント」。
アンガーマネジメントとは簡単に言うと、怒りを上手くコントロールする心理トレーニングのことを指します。
1970年代にアメリカで考案されました。
実際にアンガーマネジメントを行なった人は次のようなメリットを挙げています。
- 怒りのハードルを下げられた
- 生きやすくなった、仕事をしやすくなった
引用:【アンガーマネジメント】怒りの原因やポイント|専門家による解説付
アンガーマネジメントが注目される理由は、2020年6月に施行された「パワハラ防止法」や外出自粛によるストレスなどが挙げられています。
パワハラの疑いがかかった企業や団体は行政機関から注意が入り、改善されない場合は「企業名」または「団体名」が政府によって公表されるというものです。
(中小企業への義務化は2022年4月予定とされています)

今回は「アンガーマネジメント」の要約ポイントをまとめてみました!
怒ること自体は構わない|アンガーマネジメント

怒りは感情の中で最も攻撃性が高く、人間関係を破壊してしまう原因に多く挙げられます。
また、怒りは自分自身へ向かうこともあります。
その場合は自傷行為につながったり、過度な飲酒や喫煙なども怒りによって引き起こされてしまうのです。
一方で「アンガーマネジメント」では、「怒ること自体は構わない」と言われています。
怒っていいことは大前提にある。ただ、怒るときは上手に怒る。怒る必要がなければ怒らずに済むように。
参照:日本アンガーマネジメント協会代表「安藤俊介」
怒りのない現場は心理的安全性によって生産性を高める|アンガーマネジメント

怒りのない現場には心理的安全性が生まれ、生産性が高まります。
このことを実験したのが、一企業 Google です。
Google は4年にかけて、「プロジェクト・アリストテレス」を実施しました。
(2012年〜2016年)
「プロジェクト・アリストテレス」とは、職場で怒りのない状況を作ったり、攻撃性を排除することによって生産性が向上するかを図るプロジェクトのことです。
その結果、心理的安全性が保たれている職場は生産性が圧倒的に向上することが判明したのです。
- 自己開示ができる(心が開ける)
- 自己表現ができる(自分の言葉で話せる)
- 自己認識が良い(自分はここにいて良いと思える)
心理的安全性の高いチームは離職率が低く、収益性が高いと結論付けられています。

アンガーマネジメントは、怒りによる損失を防ぐというより、むしろプラスのエネルギーを生み出しているのです!
怒りは二次感情である|アンガーマネジメント
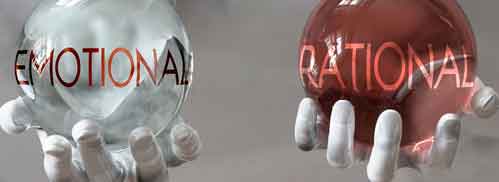
「怒りは他人のせいで生み出されている」と思うことも少なくありません。
ところが、「怒りは自分自身で作っている」とアンガーマネジメントでは主張されています。
そのため、自分自身でコントロールが可能だと言われているのです。
怒りのメカニズムを知っていくと、怒りのコントロールに役立てることが出来ます。
次の項目では、怒りの原因についてポイントを押さえていきたいと思います。

怒りをコントロールできることは心理学者アドラーも主張していましたよね!
「怒りはどう生まれる?」怒りの原因|アンガーマネジメント

「アンガーマネジメント」で紹介されている「怒りが生まれる原因」についてピックアップしました。
怒りは「〜するべき」という信念から生まれる
怒りが生まれる原因①は、「〜するべき」という信念です。
人は自分の信念と違うものを見たとき、怒りが生まれやすくなるのです。
また、「〜するべき」を意味するワードを発言することは、怒りの前兆とも言える黄色信号の状態です。
これには、「常識的に考えて、普通は、これくらい当たり前」といったワードが挙げられます。
「〜するべき」ワードを発言をしてしまった場合は、「いや、これは自分の思い込みか」と考えることで、「そもそも人には個人差がある」ということを思い返しやすくなります。
怒りは防衛感情から生まれる
怒りが生まれる原因②は、防衛感情です。
人は、自分や自身のものをひどく言われたり攻撃されたとき、自らの大切なモノを守るために怒りが発生しやすい状態になるのです。
なお、怒りは二次感情であるため、一次感情(悲しみ、虚しさ、困惑など)を防衛するために、二次感情として怒りが発生する傾向にあります。
怒りの原因とも言える一次感情に気付くと怒りに囚われなくなり、自分の正直な気持ちへと近づけるようになります。
それでは、「怒りにくいメンタル作り」や「怒りの対処法」について見ていきたいと思います。
【怒りにくいメンタルを作る方法】

怒りは、自分の近しい存在に強く出てしまう傾向があります。
例えば、「家族や親しい友人であれば何でも話せてしまう」といったケースです。
なお、近い存在に強く怒りが出ることは「甘えの行動」という見解が多いため、改善の余地が挙げられています。
そこで、怒りにくいメンタルを作ることに役立つ、「怒りにすぐ対処する方法」と「長期的に改善する方法」があります。
怒りにすぐ対処できる方法|アンガーマネジメント

怒りが込み上げてきたら
6秒STOPする
怒りにすぐ対処できる方法は、「怒りが込み上げてきたら6秒間STOPすること」です。
どうやら人間は、怒りの後に理性が追いつくまで6秒かかると脳科学研究によって判明しました。(参照:https://jfruits.com/about-anger-management)
さらに、6秒の間で怒りのコントロールに役立つ方法を「アンガーマネジメント」は紹介しています。
「今の怒りはホントは大したことじゃないかも」と気付けるために役立つ方法です。
怒ったときに数値化する

怒りにすぐ対処できる方法①は、怒りを数値化することです。
もし自分が怒ってしまったとき、その怒りの度合いに点数をつけます。
0 = 全く怒りのない状態
︙
10 = 一生忘れられないほど、命に関わるほどの激しい怒り
次の例を踏まえて解説します。
” 5人組メンバーに同じく所属しているのに、自分だけを差し置いて他の4人でパーティをしている。なぜ自分だけ呼ばれなかったのか。腹立たしい。”
このようにもし怒ってしまった場合、「今の自分の怒りは何点くらいになるだろう」と考えるようにするのです。
次の文は、自分の怒りを数値化して考えた一例です。
” 自分だけ呼ばれなくてイライラする。この怒りを点数化すると、死人が出たわけではないし、社会的な悪影響でもないから10ほどの怒りではない。また、肉体的な暴力を受けるよりマシだったと思うし、お金も盗まれたわけではない。お金も身体も無事だから5以下の怒りかな。そうなると・・・大体3くらいの怒りか “
このように怒りを数値化して考えているうちに6秒が経過し、理性が戻ってくると言われています。

ついつい2〜3点で怒ってしまう経験ありますよね・・・!
怒ったときの言葉を決めておく
怒りにすぐ対処できる方法②は、怒ったときの言葉を決めておくことです。
怒りに理性が追いつくまでの6秒間、ヒトは2~3種類の言葉しか使わなくなるようです。
そこで予め、怒ったときに声に出すワードを決めておきます。
「なんとかなる」「大丈夫」「大したことじゃない」

これらのワードは、実際に口に出すとリラックス効果があります!
怒ったときにカウントバックする
怒りにすぐ対処できる方法③は、怒ったときにカウントバックをすることです。
カウントバックとは、数字を引き算していくことです。
(例)100から3ずつ引いていくカウントバック
100→・・・97→・・・94→・・・91→・・・88→
怒った時に理性が追いつくまでの6秒の間、カウントバックが時間の経過に役立ちます。
ちなみに、深呼吸することも冷静さを取り戻せるため、怒りのコントロールに効果的とされています。

以上!
「怒りにすぐ対処できる方法」でした!
怒りを長期的に改善する方法|アンガーマネジメント

怒りの改善に役立つ長期的な方法です。自己分析にも役立ちます。
記録(アンガーログ)
怒ったときの内容をノートやスマホなどに記録します。
怒った(日付、場所、内容、点数)を忘れないうちに淡々と書き出すと、「普段、自分が何に怒っているか」が分かるようになります。
分類(ストレスログ)
怒りを感じたとき、その怒りを次のように分類します。
(その怒りは)
1.「重要か」
2.「重要でないか」
(自分の行動でその怒りを)
1.「変えられるか」
2.「変えられないか」
「重要でないなら怒る必要はなく、自分の行動で変えられないものに怒る必要はない」
こうした発想で、怒りを整理するとコントロールに役立ちます。
自己受容(サクセスログ)
怒り内容の記録(アンガーログ)に加えて自分を褒める内容をメモしていくと、自分の中に「自信と余裕」がどれだけあるかが分かるようになります。
「自信と余裕」が高いほど、自分の中で怒りが発生しにくい状態となります。

以上!
「怒りを長期的に改善していく方法」でした!
それでは最後に、「もしアンガーマネジメントを知らない人が怒ったとき」の対処法について紹介します。
「相手の怒りはどうしたらいい?」

相手の怒りは相手自身が生み出したものであるため、基本的に変えることはできません。
相手の怒りに対処するとき、大事なのは怒りの原因である一次感情に寄り添うことです。
例えば、次の例があります。
” 3人の飲食席で相手の人だけ水が出されなかったので、その人は怒っている “
この場合、怒りの原因は水がないことではなく、「3人いるのに自分だけ粗末に扱われている」という悲しみが一次感情となります。
つまり、怒りの原因となる一次感情は悲しみであり「粗末な対応をされたこと」に該当します。
よってこの場合、謝罪や丁寧な対応が相手の一次感情に寄り添うことになります。

怒りに対応するのではなく、怒りの一次感情に寄り添うことがポイントでした。
また、怒っている相手には、アドバイスではなく共感が効果的です。
【要約まとめ】アンガーマネジメント
怒りやすさは環境によって異なり、疑心暗鬼や自信のないときほど怒りやすくなります。
家族や職場以外のコミュニティとして、「自己開示および自己表現を行える場所」が怒りのコントロールに繋がります。
また、Google が実施した4年に及ぶ研究結果。心理的安全性が生産性の高まりを実証したことによって、怒りのコントロールはますます重要化されましたね。
「自分が何に怒りを感じるか」という自己分析にも役立つ書籍「アンガーマネジメント」でした!
それでは最後に「アンガーマネジメント」の要約まとめです。
- 怒りをコントロールする方法を学ぶ
- 心理的安全性が生まれる環境を作る
- 生産性が高まる
- 自己開示ができる(心が開ける)
- 自己表現ができる(自分の言葉で話せる)
- 自己認識が良い(自分はここにいて良いと思える)
- (怒ったときに)数値化する
- (怒ったときに)言葉を決めておく
- (怒ったときに)深呼吸する
- 記録(アンガーログ)
- 分類(ストレスログ)
- 自己受容(サクセスログ)

今回は科学的に怒りのコントロール法が紹介された書籍「アンガーマネジメント」の要約まとめでした!
最後までお読み頂きありがとうございました!
日本にアンガーマネジメントを伝えた第一人者「安藤俊介」さんについても紹介
マンガ版「アンガーマネジメント」