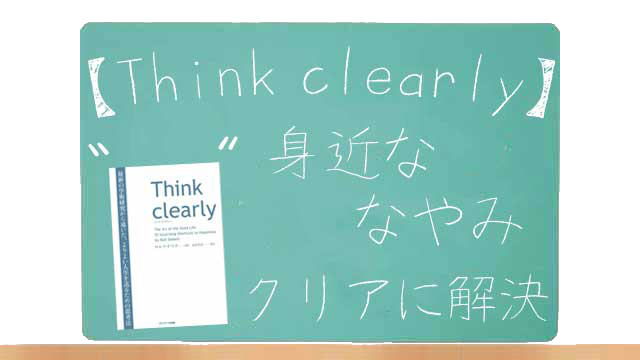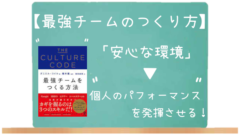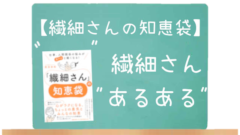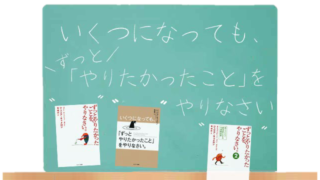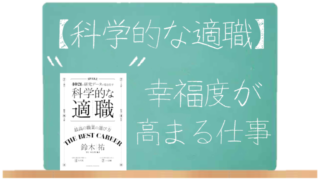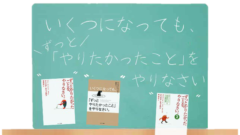2019年4月に出版された「Think clearly」(著:Rolf・Dobelli/ロルフ・ドベリ)。
身近な悩みをクリアに解決してくれる内容の本です。
続編となる「Think Smart」が登場したところ、
「Think clearlyとThink Smartはどっちがいい?違いは何?」
といった声があったため、その違いを見るために先に「Think clearly」を要約しています。

今回は「Think clearly」の要約ポイントを見ていきたいと思います!
「Think clearly」とは?要約すると?
「Think clearly」は要約すると、
「自分で出来る事とやりたい事を線引きして、取捨選択のルールを決めると人生はクリアになる」といった内容です。
多くのビジネス本には、「正直でいるべきだ」「嫌でもやるしかない」といった主張が見られますが、これと比較すると「Think clearly」は「嫌なものは断ろう」や「本音は出すな」と主張していることが特徴的です。
| 「Think clearly」 | 多くのビジネス本 |
| 本音は出すな | 正直でいるべきだ |
| 嫌なものは断ろう | 嫌でもやるしかない |
このことからも「Think clearly」は、自分にできる事とできない事、やりたい事とやりたくない事の線引きに役立つ参考書と言われているのです。

それではポイントを見ていきたいと思います!
取捨選択のルールを作る

「自分に出来る事と出来ない事」「やりたい事とやりたくない事」
これらを線引きする方法を教えてくれるのが「Think clearly」です。
その一つ目として、「取捨選択をするときに役立つルールを作ること」が解説されています。
これは、物事を選択するとき、「自分で予め決めたルールで判断すると身の回りの悩みを解決できる」というものです。
それでは「Think clearly」が紹介する、「取捨選択のときに役立つルール」の例をいくつかピックアップします。
安易に頼み事に応じない

身の回りの悩みを解決できる取捨選択のルールの一つは、「安易に頼み事に応じないようにすること」です。
人が安易に頼みごとに応じてしまう原因は、人に好かれたい願望があるからです。
例えば、次のような頼み事をされると断りづらいですよね。
「今夜のパーティ、あなたにどうしても来て欲しいです」
このように好意を受けて誘われると、人は人間の性質上として、断りづらくなってしまうのです。
それでは、人間の性質について少しフォーカスしてみます。
心理学とITデータを用いた研究結果では、人間は「しっぺ返し戦略」で生き残った生物だと判明しています。(※しっぺ返し:何かをされたら仕返しをする)
参照:Think clearly
このことから、人間らしさとは「GIVE & TAKE」の関係を取ることにあると言えるです。
(※GIVE & TAKE:恩を受けたら返す)
また、一方的に与え続ける「GIVE & GIVE」や受け取り続ける「TAKE & TAKE」は、どこか機械的な印象をもつため、人間らしさから離れている行動になります。
「5秒決断ルール」を活用する

身の回りの悩みを解決できる取捨選択のルールの一つ、投資家ウォーレン・バフェットが主張した「5秒決断ルール」というものがあります。
5秒決断ルールとは、何かを決断するとき「5秒迷ったら答えはNOだ」と答えを出すことです。
決断するときに5秒以上も悩んでしまう場合は、人間に備わる「しっぺ返し戦略」が揺らいでいる状態と言えるのです。
つまり、何かを決断するときに5秒以内でYESが出るときはYESとなります。

5秒以内でYESと決断できない場合はNOという事ですね!
優柔不断とおさらば出来そうです!
「能力の輪」「尊厳の輪」で断る

「能力の輪」「尊厳の輪」を活用すると、断るときの基準をハッキリさせることができます。
- 「能力の輪」
→ 自分の能力で出来ない事は断る - 「尊厳の輪」
→ 論理より主義で断る
「能力の輪」自分が出来ないことは断る
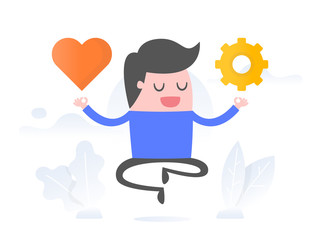
「自分の能力で出来ないことは断る」といったルールの範囲を「能力の輪」と言います。
自分ができる事の「大きさ」ではなく、自分に何ができて何ができないかの「境界線」にあたります。
能力の輪を意識して、「自分のジャンルをはっきりさせる」「自分がやれることをやる」といったように活用すると良いでしょう。

「自分がどれぐらいできるか」よりも「自分に何ができるか」を優先的に考えると良さそうですね!
「尊厳の輪」自分に出来る事だけどやりたくないと主張する

「論理より自分の主義を優先する」といった決め事の範囲を「尊厳の輪」と言います。
例えば、「自分にできることだがやりたくない」と思える物事が挙げられます。
「報酬が良くて自分の能力で出来る案件だけど行うと自分らしさが失われてしまう」
そのように感じた場合は、自分の中で「尊厳の輪」が働いているのです。
人は仕事に対してお金が積まれた場合、主義(自分らしさ)または論理(お金)で揺らいでしまいます。
このとき多額のお金が支払われる場合、人は自分らしさよりもお金を選んでしまう傾向があるのです。
ところが「Think clearly」では、報酬が多く支払われる場合でも、「嫌と思ったことは断る」ことを奨めています。その理由の一つとして、「悪魔に魂を売るな」という言葉が古今東西(世界各地)にあることが挙げられています。
アウトプットにいい取捨選択

ここでは「Think clearly」が紹介するアウトプットにいい取捨選択のポイントを紹介します。
本音をさらけ出さないようにする
人間は本音をさらけ出したい傾向にありますが、「Think cleary」は本音をさらけ出さないようにと主張しています。
その理由は、感情は当てにならないからだそうです。
例えば、AさんがBさんを苦手でその事をネットに書き込んだとします。ところが、BさんがAさんを応援していたことをAさんが知ると、Bさんの事が苦手だという感情はころっと変わってしまったのです。
自分の感情が判明しないまま、削除しづらいインターネット等に書き込んだりアウトプットしてしまうと、取り返しのつかない事態につながることもあります。

SNSは本音で書き込みしやすく、感情の強いコメントが多くあるので注意ですね。
本音をさらすのではなく日記をつけると良い

日記をつけてみると、1ヶ月前の自分と今の自分との違いが見られます。
1ヶ月前の自分の本音を見たとき、「こんなこと口にしなくてよかった」と感じることがあるのです。
また、外で接するときの人格をつくると良いです。
わからないものは「わからない」と答えていい

「自分が詳しくないことや興味のないことに意見するべきではない」と著者は主張します。
なぜなら、自分にとってメリットがなく、損となってしまいやすいからです。
例えば、新聞やニュースなどで自分にとって詳しい分野でなく興味もない情報が入ってきたとき、人は2通りで判断します。
この2通りの判断とは、自分にとって「ポジティブかネガティブか」または「好きか嫌いか」の2つです。
つまり、人は情報が入ってきたとき、その情報について「ポジティブかネガティブか」「好きか嫌いか」でしか発言できない傾向を持っているのです。
無意見や沈黙は知性を表す
自分が詳しくないことや興味のない情報に対して意見を求められたときは、「わからない」と答えたほうが良いと著者は主張しています。
なぜなら社会の情報が複雑すぎるため、2通りでしか判断できない人間が答えを示すことは安易だと考えられるからです。
聞かれた質問に対して「この問題は複雑なのでわからない」とした無意見や沈黙は、知能の低さを表さず、むしろ知性を表す回答だと言われています。
インプットにいい取捨選択

ここでは、「Think clearly」が紹介するインプットにいい取捨選択のポイントをまとめています。
情報収集をしすぎてはいけない
作家シオドア・スタージョンの主張があります。
「すべての読み物の90%はゴミだ」
引用:Think clearly シオドア・スタージョン
アプリなどによるニュース配信が普及した現代では、多くの人が不必要な情報収集を過剰にしていると著者は主張します。

「ニュースを多く見た方がいい」と思う方もいるかもしれませんが、「Think clearly」では、インプットするニュースの量は制限し、自分が読むべきものかどうかを精査することを勧めています。
信頼できる人とだけ付き合う

好感と信頼が大事だと「Think clearly」は主張します。
「Think cleary」の著者は年に一回、付き合いをやめる人の名前を紙に書いて投げ捨ててスッキリしているようです。
良い本は繰り返し読む
本を読むとき、多くの人が一回読みだけで終えてしまう傾向にありますが、2回読むと理解度が3%~30%に上がると言われています。

繰り返す読むことは理解度を上げてくれるのです!
当サイトでは「話題な本」を積極的に要約していますので、ぜひ参考にしてみて下さい!
大きすぎる夢を持たないようにする

Think clearly の著者は「大きすぎる夢を持たないようにすること」を指摘しています。
ここでは、そのことを大きく主張している箇所をピックアップしています。
「あなたに世界は変えられない。なぜなら、偉人ですら世界を変えたわけではないのだ」
「スティーブ・ジョブズがいなかったらiPhoneは本当になかったか。また、ビル・ゲイツがいなかったらWindowsは本当になかったのか」
「多くの競合他社がOSやデバイスを必要だと考えていた。そのなかで、あくまでもジョブズの会社が先んじて社会に普及させたにすぎない。人間は偶然と偶然の衝突にさらされて、その勝利者を崇めすぎているのではないか。スティーブ・ジョブズがいなくてもiPhoneはあったのだ」
参照:「Think clearly」
これは要約すると、先駆者は偶然に現れただけなので、「世界を変える」といった大きすぎる考えを持たなくて良いと言い換えられるのです。

ジョブズの秘話は他にもあります!
前の記事も参考にしてみて下さいね!
勝つことより負けないこと
勝つことより負けないことが大事だと著者の主張があります。
これは例えば、航空パイロットは早く飛ぶことより安全第一を心掛けていることや、プロテニスプレイヤーは相手のミスを誘うようにプレーするといったことが挙げられます。
何を手に入れるかより何を避けるか
人は行動してリターンを得るアップサイド(報酬や人気が上がるなど)にはすぐ慣れますが、その逆を意味するダウンサイドには慣れることはないと著者は主張します。
ダウンサイド(ストレスにさらされ続けることや何かの依存症)に陥ると、長期間にかけて負荷がかかりやすく、時間が解決することに期待できません。
つまり、人間は辛いことには慣れないため、辛いものを避ける戦略が必要だと著者は主張します。
世界を変えたいのか、人生を変えたいのか

著者の主張があります。
「世界のことに対して気に病む必要はない」
「たいていのボランティアは意味がない。君がボランティアをするのは君自身が納得したいからだ。運び作業なら君がやるより、力持ちの人に報酬を渡して頼んだほうがずっと効率がいい。だから、君は君の人生を全うするのだ。世界に貧困がはびこっているのはたしかだ。しかし、人は世界の悲しみをすべて悲しめない。だから君がやることはひとつ、自分の中で物事を線引きして、自身がやるべきことだけに集中するのだ。外部のことを気にするから混乱する生活を送ってしまうのだ」
参照:「Think clearly」
つまり簡単に言い換えると、
「自分の中で物事をはっきり線引きしてクリアにしていき、自分がやるべきことを果たすことが、何事においても最も効率良い方法である」
といった所かと思います。
これが「Think clearly」の大きな主張にあたると言われています。
【要約まとめ】Think clearly
今回は「Think clearly」の全52原則の中からいくつか要約させて頂きました。
それでは最後に、「Think clearly」要約ポイントをまとめていきます。
- 自分のできる事とやりたい事を理解する
- 「できる事とやりたい事」以外には干渉しない
- 自分の内面に集中してやりたい事を貫く
- 簡単に頼みごとに応じない
- 5秒決断ルールを使う
- 「能力の輪」「尊厳の輪」で断る
- 本音をさらけ出さないようにする
- 本音をさらすのではなく日記をつける
- わからないものは「わからない」と答える
- 情報収集をしすぎてはいけない
- 信頼できる人とだけ付き合う
- 良い本は繰り返し読む

今回は身の回りの悩みを解決してくれる「Think clearly」の要約まとめでした!
最後までお読み頂きありがとうございました!