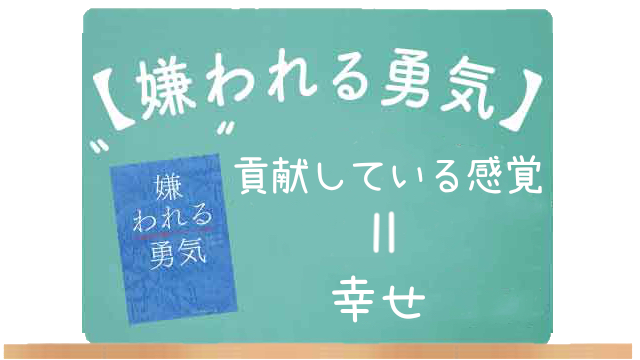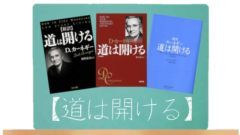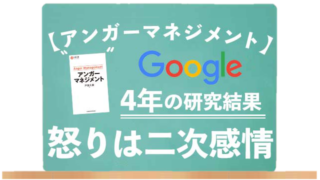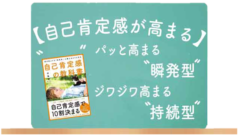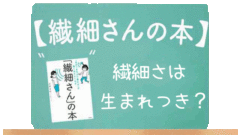2013年に出版された岸見 一郎さん、古賀 史健さん著作「嫌われる勇気」。
発行部数が世界440万部を突破した大人気本です。
その人気の理由は、次のように多くの人に共通した疑問を解消しているからです。
- 「人は変われるだろうか?」
- 「この世界は複雑じゃない?」
- 「誰もが幸福なんてありえるの?」
「嫌われる勇気」は多くの人から共感を得ている本と言われています。
また、この本の内容は対話形式で構成されているため読みやすく、また音声で聴けるオーディブル版と相性が良いため、「オーディブル売上ランキング」では堂々の1位を獲得するほどの人気があります。参照:「オーディブル売り上げランキング2020(ビジネス本)」
この記事では「嫌われる勇気」が主張するポイント「幸福に生きるための考え方」を3つに分けて要約しています。

今回は「嫌われる勇気」のポイントを要約してまとめました!
幸福に生きるための考え方①「人は変われる」

幸福に生きるための考え方①は「人は変われる」ことです。その理由として次が挙げられます。
- 人はトラウマ、怒り、劣等感を道具として利用している
- 怒りはコントロールできる
参照:「嫌われる勇気」
結論から見ると、人がトラウマや怒り、劣等感を道具として使う理由は、「自分を演出するため」や「言い訳を正当化するため」などが挙げられており、「自分が都合よく利用しているものは自身で変えられる」という結果です。
それでは、それぞれ理由のポイントを見ていきたいと思います。
人はトラウマや怒り、劣等感を道具として利用している
人が変われる理由の1つ目、「人はトラウマや怒り、劣等感を道具として利用している」について見ていきます。
ここでは心理学者アルフレッド・アドラー(1870〜1937)の「目的論」が注目されています。目的論とは「今ある目的のために自分が都合よく過去の出来事を解釈して利用する」といったものです。
例えば、「外に出たくないという目的を果たすための手段として、過去に犬に噛まれたからという経験を利用する」が挙げられます。
つまりアドラーによると、「人間は楽な現状を維持するため過去のせいにする傾向がある」と主張しているのです。
「嫌われる勇気」では他にも例として、赤面症の人との会話が挙げられています。
▶︎赤面症の人の悩み
「すぐ緊張して顔が赤くなるから自分の思いを伝えられない・・・」
▶︎アドラーの回答
「それは赤面症を理由にして、思いを伝えられない状態を自分で作っているだけだよ」

人はコンプレックスを言い訳にして行動しない理由を作ってしまう傾向があるのです!
怒りはコントロールできる
アドラーは続けて、怒りはコントロールできることも主張しています。
参照:「嫌われる勇気」
その1「飲食店の例」

飲食店で利用者のシャツに水がかかってしまったときに怒りがコントロールできることを表した例です。
店員のミスで利用者のシャツに水がかかってしまい、利用者は怒っています。利用者の怒りがあまりにも止まらなかったため、ここでアドラーが「怒りはコントロールできないものでしょうか?と尋ねたところ、利用者は「怒りをコントロールできない」と答えました。これに対してアドラーが言いました「では、あなたがナイフを持っていたらその店員を刺していましたか?」。すると利用者は「いやナイフでは刺さない・・・」と答えたため、アドラーは「怒りはコントロールできるではないですか」と主張したのです。
その2「電話の例」

電話に出るときとっさに怒りをコントロールした例です。
大喧嘩の途中で相手と別れた後に家の電話が鳴りました。さっきの喧嘩相手だと思い、声を荒げて怒りの態度で電話に出ますが、電話先の相手は別の人物でした。このとき、とっさに声のトーンを落ち着かせて電話の対応に入りました。

こちらでは電話相手が別の人だと気付いたとき、怒りを落ち着かせていることが分かりますね!
幸福に生きるための考え方①「人は変われる」まとめ
怒りはコントロールできることを「嫌われる勇気」は主張しています。
自分が都合よく利用しているもの(怒り、トラウマ、コンプレックス)は自分で変えられるので、人は変われるということですね。

怒りは短時間で改善できる方法もありますので、次の記事も参考にしてみてくださいね!
【嫌われる勇気】「世界はシンプル」

「嫌われる勇気」が主張する「世界はシンプル」の理由として、次の3つが挙げられます。
全ての悩みは対人関係

人間の悩みは全て対人関係にあると「嫌われる勇気」は主張しています。
対人関係における悩みのポイントは「自分の事と人の事を分けること」です。

自分の行動結果が、「自分のためになるか」「人のためになるか」を区別することがポイントです!
承認欲求における注意事項

人には承認欲求があります。
承認欲求とは、「他人から認められたい、自分を価値ある存在として認めたい」といった欲求を表す心理学用語です。
承認欲求の中でも自己肯定感や自由のために、やってはならない注意事項が「嫌われる勇気」で解説されています。ここではそのポイントをまとめました。
禁止事項(1)限度を超える競争
競争をしすぎると、競争相手が仲間でなくなってしまう場合があります。そのため、競争するときは限度を超えないように意識しておくと良いと述べられています。
また「嫌われる勇気」では次のように主張されています。
「競って勝たないと、自分にはまるで価値がない」。そのようなことは思わなくて良い。
参照:「嫌われる勇気」

競争だけが全てではないですね!
禁止事項(2)褒められようとすること
「出来たら褒める」「出来なかったら褒めない」といった賞罰教育は、褒められないと何もできない精神を生んでしまいます。
「近所の掃除をしていたが誰からも褒められないので止めた」といった例もあります。
褒めてくれるから何かをするという考え方は、自分の行動を他人に決めさせていることになるのです。

褒められようとすることは、自分が自由な状態でなくなるので褒められようとしなくて良いのです。
禁止事項(3)褒めること
褒めることは、能力の上の人が能力の下の人に評価する行為とされます。
そもそもそうした行為は必要ではないと「嫌われる勇気」は主張しています。

褒められた側は「自分はそのヒト(褒めた人)より下なんだ」と潜在的に思ってしまうのです。
感謝する横の関係を築く

人間関係において、相手を褒めることは縦の関係(上下関係)を生んでしまいます。
そこでアドラーは、縦の関係ではなく横の関係を築くことを推奨しています。
縦の関係が「褒めること」に対して、横の関係は「感謝すること」です。
- 褒める →縦の関係
- 感謝する→横の関係
「褒める」から「感謝する」へ変えることによって、誰かの評価で自分の行動が規制されない自由な状態になります。

つまり、「褒めてくれるから行動する」や「行動してくれたから褒める」といった縦の関係から解放されるのです。
世界はシンプルな理由「たいていが自分の課題ではない」
自分の課題もしくは相手の課題であるかを判別することは重要です。
なぜなら、相手の課題は自分ではどうすることも出来ないからです。
「自分の行動で相手が嫌うかは、自分が決められることではない」
参照:「嫌われる勇気」
「嫌われる勇気」では、「嫌われるのはイヤだ」と思う人にアドバイスしている箇所があります。
たとえば大食いをしている場合、「ものすごく食べるね・・・」と見る人もいれば、「ご飯にがっついて可愛い」と見る人もいます。
これは自分がどう見られようと相手側の問題なので、自分の課題ではありません。

自分と相手どちらの課題であるかを判別できると、自分の課題だけに集中すれば良いことに気づけます!
「全ての悩みは対人関係」▶︎(だから)▶︎「自分の課題だけに集中する」▶︎(よって)▶︎「世界はシンプル」といえる
【嫌われる勇気】「誰もが幸福になれる」

「嫌われる勇気」は幸福について、心理学者アルフレッド・アドラーが提唱した「共同体感覚」を挙げています。
「共同体感覚」とは、「他の人に貢献できている感覚」のことです。
「誰もが幸福になれる」と言える理由は、他の人に貢献できている感覚を誰もが持てることにあるのです。
他の人に貢献している感覚が幸せをもたらす

心理学者アルフレッド・アドラーによると、幸せは共同体感覚によって得られると主張しています。
例えばお金持ちであっても、幸せであるかどうかは「他者に貢献できている感覚が有るか無いか」によるのです。

他者に貢献するには、自己受容と他者信頼がポイントです!
「自己受容」
自己受容とは、ありのままの自分を受け入れることです。
ありのままの自分を受け入れるためのポイントは、自分自身の「良い所」と「良くないと思う所」をそのまま受け入れていくことにあります。

自分が出来ないと思う所から受け入れていくと良さそうです。
ありのままの自分を受け入れると、「自分は〜が出来ないからどう対応をしようか」という考えができるようになります。
なお、自己受容は自分の「行為」よりも自分の「存在」を自己受容するほうが望ましいとされます。
○存在の自己受容
→自分が家庭にいることで家族は幸せだと思ってくれるだろう。
×行為の自己受容
→家族を養うために自分はお金だけ稼げばいいのだろう…。

存在の自己受容が重要とされています!
「他者信頼」
他者貢献をするには、無条件な信頼によって他者を「仲間」と思うことが重要になります。
信頼:無条件で信じること
信用:条件付きで信じること
たとえば道端で困っている人を手助けすることは、無条件な「信頼」によって成り立っています。
相手はこちらが「信頼しているか」「信頼していないか」をみている。それなら、まず信頼することだ。相手が裏切るか裏切らないか、それは相手側の問題で自分の問題ではない。
参照:「嫌われる勇気」心理学者アルフレッド・アドラー

他者信頼ができると、「他者貢献」ができるようになります!
「他者貢献」
心理学者アルフレッド・アドラーによると、他者に貢献することは自分自身に幸せをもたらします。
例え、億万長者であっても働いている人が沢山います。その人たちが働く理由は、お金のためではなく貢献をしたいから働くようになります。「お金を稼ぐ」→「どうすれば人に貢献ができるか」という考えにシフトチェンジするようです。
「他者に貢献している感覚さえあれば、そのとき、人生の幸福にたどり着いている」
アルフレッド・アドラー

これが世間でよく耳にする「アドラーの心理学を学んだとき誰もが幸せになれる」と言われる由縁です。
【要約まとめ】嫌われる勇気
よくアドラー本では「アドラー心理学を学んだとき誰もが幸せになれる」と主張されていますが、いつでもどこでも幸せを得られる「共同体感覚」のことを指しているのでしょうね。
アドラー心理学は「心理学が初めて」という方によくオススメされているので、「嫌われる勇気」から導入した人も多いと言われています。
それでは最後に、「嫌われる勇気」の要約をまとめます。
- 人は変われること
- 世界はシンプルなこと
- 誰もが幸福になれること
- 「人はトラウマ、怒り、劣等感を道具として利用している」
- 「怒りはコントロールできる」
- 全ての悩みは対人関係
- (褒められようとしてはいけない)
- たいていが自分の課題ではない
共同体感覚が幸福であるため、貢献する感覚によって誰もが幸福になれる。
- 自己受容
- 他者信頼
- 他者貢献
- 自由とは他者から嫌われることである
- トラウマは存在しない
- 人は変われる!誰もが幸福になれる!
引用:嫌われる勇気

今回はアドラー心理学が満載の人気本「嫌われる勇気」の要約まとめでした!
最後までお読み頂きありがとうございました!